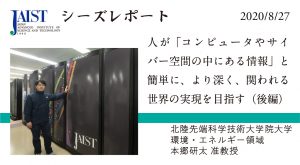
本郷研太准教授の研究シーズを紹介する2回目。機械学習、AI、そしてスパコンを縦横無尽に使ってマテリアルズ・インフォマティクス(※)の研究を進め、新しい化合物の発見に迫る姿とその想いに迫ります。
(※)マテリアルズ・インフォマティクス=AI等の高度な解析ツールを活用して、新しい材料を開発する研究分野
私たちの生活と密接な関わりを持つ材料開発の分野
マテリアルズ・インフォマティクスでより効率的に
新しく開発された材料が私たちの暮らしに変化をもたらしたケースは枚挙にいとまがありません。例えば、新しい材料を導入して普段使いの製品が改善した事例として、スピーカーの音質を見てみます。
以前は、スピーカーの音質を改善するには電気的に制御することが主流になっていました。その後、ネオジム磁石という強力な磁石が登場して、それをスピーカーの中に組み込むと劇的に音質が向上しました。これはあくまで一例で、私たちの身のまわりのあらゆるところで、新しい材料による製品が生活の質的向上に役立っています。
 共同研究でも積極的に活用されている本学保有のスパコンとその前に立つ本郷准教授
共同研究でも積極的に活用されている本学保有のスパコンとその前に立つ本郷准教授
当然ながら、材料開発の道のりは決して平坦なものではありません。前編で指摘しましたが、那由多の数だけあるとされる化合物の組み合わせを前に、人間ができることには限界があり、例え新たな材料、化合物に目星を付けても、その合成や特性の確認にはある程度の時間が必要になります。
本郷准教授は、「その点で言えば、私のアプローチ法は、まずこういう性質を持った材料は、だいたいこんな材料だということをコンピュータ、いわゆるAIに教え続けて大量のデータを確保します。次に、このデータをベースとしてスパコンで膨大な数のシミュレーションを行うことで、今までよりずっと効率的に新しい物質を見つけられるようになりました」と、マテリアルズ・インフォマティクスによる材料開発の優位性を話します。さらに、「例えば、単純な化合物から新たな分子結合を始めるケースでも、AIが分子をどんどん改善させていって欲しい分子に近づけていくので、斬新で、これまでに見たことがない新しい分子がどんどん出来てきます。AIの技術を用いたこのような研究を続けていくことで、そのうちに狙っている、欲しい属性を持つ化合物が見つかることにつながるのだと思います」と続けます。

既に誰も見たことがない化合物をコンピュータ内で確認
課題を解消する未知の化合物発見の最先端手法を提案
マテリアルズ・インフォマティクスの研究の進展によって、本郷准教授の研究室では、今まで誰も見たことがないような化合物をコンピュータの中で見つけられるようになっています。一例を挙げると、AIを使って高熱伝導率のポリマーを探索し、実際に合成することに成功しています。ポリマーは他の工業材料に比べてかなり熱伝導率が低い材料ですが、熱伝導率が高く放熱性があれば、金属材料の代替として使うことができ、デバイスの軽量化につながることも期待されます。
本郷准教授は、「私は新しい化合物を発見する手法の開発が専門なので、電池でも磁石でもポリマーでも、あらゆる面白そうな化合物の発見や材料開発のお手伝いができると思います。共同研究先とは、一緒に材料開発に汗する中で、チャンピオンデータ(最も効果の顕著な結果)を出したいですね」と、共同研究にかける想いを熱く語ります。
材料開発に興味を持ったのは幼き頃の刀鍛冶への憧れ
最先端の研究者は歴史好きの趣味を持つ意外な一面も
本郷准教授の子どもの頃の夢は、刀鍛冶になることでした。その後、大学では金属材料の研究に進み、海外を含む研究機関を経て現在に至った経緯をみると、材料開発に向けた素地は日本刀に興味を持った幼い頃からあったのでしょう。
時々、研究室のメンバーや留学生を誘って兼六園や金沢城に足を運び、歴史のレクチャーをするほど歴史好きでもある本郷准教授。話し好きで温厚な人柄は、気軽に問い合わせや相談ができる雰囲気に満ちています。
 兼六園で学生に説明する本郷准教授
兼六園で学生に説明する本郷准教授
<シーズレポート>材料開発の前に立ちふさがる様々な課題に、スーパーコンピュータを駆使して立ち向かう(前編)はこちら。
本件に関するお問い合わせは以下まで
北陸先端科学技術大学院大学 産学官連携本部
産学官連携推進センター
Tel:0761-51-1070
Fax: 0761-51-1427
E-mail:ricenter@www-cms176.jaist.ac.jp
■■■今回の研究に関わった本学教員■■■
環境・エネルギー領域
本郷研太 准教授
