
-

西村拓一教授
東京都出身。トランスフォーマティブ知識経営研究領域。「熟練者を超えるAIを生み出す」というビジョンのもと、暗黙知の構造化と体得支援技術の研究を行っている。 -

国見有さん
2024年入学
神奈川県出身。博士前期課程。教育学部卒。研究テーマは「モーションキャプチャを用いた社交ダンサーと非運動習慣者の身体基礎動作の比較」。 -

オウ・ヘイイさん
2024年入学
中国雲南省出身。博士前期課程。研究テーマは「日本の宿泊業における外国人従業員のサービス能力向上のための知識構造化:中国の従業員の職場適応に着目して」。 -

龍大地さん
2024年入学
兵庫県出身。博士前期課程。情報科学科卒。研究テーマは「コールセンターオペレーターの知識構造化と業務支援策の提案」。 -
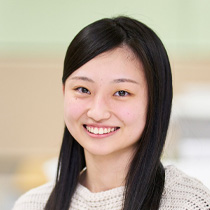
鏡味ほのかさん
2024年入学
愛知県出身。博士前期課程。理工学部卒。研究テーマは「表現力豊かなピアノ演奏における身体的特性の調査」。
北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)の西村(拓)研究室を選んだ理由は?

国見さん
「自分の得意を伸ばす」という研究室の方針に共感したからです。教育学部出身で理系のバックグラウンドはなかったものの、身体の動きを科学的に分析するバイオメカニクスを学んでいたこともあり、人工知能には興味がありました。そこでAIの分野で研究できる環境を探していたときに見つけたのが、西村研究室のホームページ。ひと目見た瞬間に「ここなら自分のやりたいことを尊重してもらえる」と感じました。

オウさん
先生の人柄と研究室の雰囲気に魅力を感じました。日本語を学び始めたばかりでうまく話せなかった私にも、西村先生はとても優しく接してくださり、研究室配属の相談にも親身になってくれました。やさしい日本語で研究室のことを教えてくれた、先輩方のサポートもうれしかったですね。西村研究室は学生の意見を尊重してくれるので、安心して研究に取り組める環境だと感じています。

龍さん
専門学校でシステム開発を学んでいたのですが、その中で「システムがいくら完璧でも、使いづらければ意味がない」と気づき、ユーザー視点で本当に役立つシステムの設計や、運用現場での課題解決につながる研究ができる場所を探していました。そんなときに西村研究室のことを知り、ここでなら人工知能をツールとして自分の考えを生かした研究ができるのではないかと思いました。
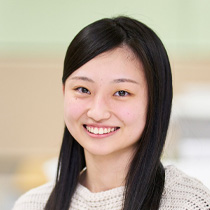
鏡味さん
大学時代から「ピアノ演奏における熟練者と初心者の演奏の違いを科学的に分析する」という研究テーマに取り組んできました。その上で、西村先生の「人の動きをデータとして扱い、分析する」というアプローチが、自分の研究とも深くつながると感じ、配属を志望しました。また、研究する環境も大切だと考えていて、この研究室の「自由で活気のある雰囲気」が自分に合っていると感じました。

西村教授
オウさんは入学後に配属が決まったけど、ほかの3名は入学前に研究室の見学をして、すでに進学の意志を固めていたんですよね。私自身、ここでは知識を身につけるだけでなく、「人としての生き方」「研究者としての姿勢」「どういうことを楽しいと感じるか」といった部分も大切にしてほしいと思っていて。ここで学んだ仲間とのつながりが、一生の宝物になってくれたらうれしいですね。


現在はどのような研究を行っていますか?
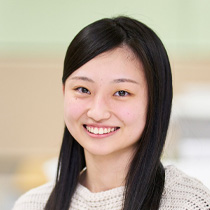
鏡味さん
同じ楽曲をピアノで演奏しても、人によって音の響き方や表現が異なります。私はこの違いが、演奏者の身体の使い方や動きによる影響だと考え、ピアニストの身体の動きをセンサーで計測し、演奏中の姿勢や手の使い方、呼吸変動などをデータ化しています。さらに、そのデータを初心者と比較して熟練者特有の動作パターンを抽出し、演奏指導や練習法の改善に役立てることで、より効果的なピアノ教育に貢献したいと考えています。

オウさん
日本のホテル業界で働く外国人従業員のサービス向上を目的とした、知識構造化に取り組んでいます。日本独自の「おもてなし」文化に慣れていない外国人従業員は、業務中に戸惑うことが多々あります。そこで、実際にホテルで働く外国人従業員へのインタビューを実施し、業務上の課題や学び方を分析。さらに熟練者が持っている暗黙知(経験的なスキルや接客のコツ)を整理・構造化することで、業務マニュアルや教育システムへの活用を目指しています。

国見さん
ダンサーと一般の人の身体の動きの違いを明らかにする研究を行っています。具体的には、スクワットや片足立ちの動作を対象に、関節の動きや重心の変化をセンサーで計測・分析し、ダンサー特有の動きの特徴を数値化。それによって、リハビリの現場でより効果的な運動指導が可能となり、アスリートのトレーニング方法もより科学的に改善できるなど、スポーツや医療分野への新たな知見の提供を目指しています。

龍さん
次世代のコールセンターにおけるベテランオペレーターの知識構造化が、主な研究テーマです。経験豊富なオペレーターの判断基準やノウハウの属人化が課題となっている中で、ベテランの対応方法を分析し、知識を体系化することで、新人オペレーターの教育や業務効率化の支援を目指しています。実際にコールセンターに出向き、ヒアリングや業務観察を行い、AIやシステムで活用できる形に整理するまでが、おおまかな研究の流れとなっています。
西村(拓)研究室の魅力を教えてください。

オウさん
研究室の雰囲気が明るく、学生同士が自然と協力し合っているところが好きです。みんなで助け合いながら研究を進められるので、一人で悩むことが少ないんです。研究室の一角にはオープンスペースもあって、そこでみんなに日本での生活の悩みを相談できるのもうれしいですね。研究室に行くといつも誰かが何かしらの活動をしていて、みんなが目標に向かって努力している姿を見て、いつも刺激を受けています。
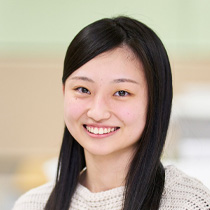
鏡味さん
私も、オープンスペースの存在を魅力に感じています。大学院に進学するにあたり、「この研究をもっと深められるのか?」という不安もありましたが、仲間との意見交換やサポートを通じて自信を持てるようになりました。研究の進め方についてアドバイスをもらえるのも心強いですね。また、初めての一人暮らしで環境の変化に慣れるまで少し時間がかかりましたが、周りの先輩方が支えてくれたおかげで、安心して研究に集中できました。

龍さん
先生との距離が近く、気軽に相談できるところです。研究室によって先生との関わり方もさまざまですが、西村先生はとてもフレンドリーで、忙しい中でも親身になって対応してくれます。また、研究の進め方も自由で、自分の興味に沿って深く掘り下げられるのが魅力です。実際に企業のコールセンターでの現場調査を提案した際も、先生は「面白そうだね!」と親身になってサポートしてくれました。

国見さん
僕も自由に研究できる環境に魅力を感じています。西村先生は学生の考えをしっかり聞いてくれるし、研究の方向性も押し付けられることなく議論しながら決められるので、十分納得した上で「自分が本当にやりたい研究」に取り組むことができます。また、研究だけでなく、キャリア面でのアドバイスや、学外の研究コミュニティを紹介してくれることもあり、そのおかげで新しいつながりができたり、より多角的な視点で研究を進められたりもしています。

西村教授
私の能力には限りがありますが、学生たちはそれぞれ異なる視点や強みを持っています。教える側でありながら、「そんな世界があったのか!」と学生の発想に驚かされることも少なくありません。だからこそ、学生が自分のやりたいことをとことん突き詰められる環境を作りたい。彼らの興味や意欲を伸ばすことが、研究室全体の成長につながるはずです。最終的には、その成果が新しい知見として世の中に発信されることを期待しています。


研究をする上で心がけていること、また自分自身の成長を感じる瞬間は?

国見さん
研究は一人で考え込むと行き詰まりやすいので、方向性を見失いそうになった時点で先生や先輩に相談し、効率的に解決できるよう心がけています。また、研究を進める中で、過去のノートやメモを見返したときに「当時は分からなかったことが、今なら理解できる」と気づく瞬間があり、そのたびに自分の成長を実感しています。

オウさん
私が研究を進める上で大切にしているのは、「少しずつでも毎日学び続けること」です。研究は長期的なプロセスを積み重ねていくものなので、一度中断すると再開するのが難しくなります。それを避けるため、平日は欠かさず論文を読んだり、研究の進捗について話し合ったりしながら、研究の流れを止めないよう意識しています。

龍さん
熟練者の暗黙知を構造化するには、現場の実態を深く理解しなければいけません。そのため、論文や書籍に加え、ニュース記事や業界の動向まで幅広く情報を収集できるよう、常にアンテナを張ることを心がけています。また、「AIで支援できる部分」「人間の判断が必要な部分」を明確にすることが、より実践的な研究につながると考えていて、実際にコールセンターを訪れて、業務を観察することも重視しています。
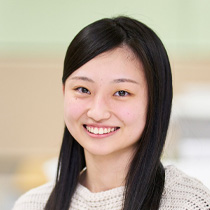
鏡味さん
研究中は、実験やデータ分析に集中するあまり、本来の目的からずれることもあります。そのため、常に「この研究が何のためにあるのか?」を意識しながら進めることを心がけています。また、研究を深く掘り下げることは重要ですが、それだけでは視点が狭くなってしまうので、異なる視点を取り入れることで、より広い視野で研究を進められるよう意識しています。入学時と比べて、論理的に考え、伝える力が向上したことが、一番の成長だと感じています。

西村教授
論文を読むときは知識を詰め込むだけでなく、「知識が生まれた背景」「研究に込められた熱意」を感じ取ることが大切です。研究が自己満足で終わらないよう、社会や他者にどう役立つのかを考える視点やウェルビーイングへの配慮も意識してみてください。また、失敗を積み重ねることも重要です。 論文のリジェクトや仮説の崩壊は誰にでも起こりますが、そうした経験を通じて、より強い研究者になれるのです。

卒業後の進路について。将来はどのような職種を目指していますか?

龍さん
IT分野の職種に就きながら、ITとは直接関係のない業界の企業に進む予定です。なぜIT企業ではなく異業種のIT職を選んだのかというと、その業界特有の知識や技術に触れながら、ITを活用して業務を効率化する仕事に魅力を感じたからです。なかでも重視しているのが「社会に不可欠な役割を果たしているか」という点。安定性のある業界でDX推進に関わることで、長期的なキャリアを築いていきたいと考えています。
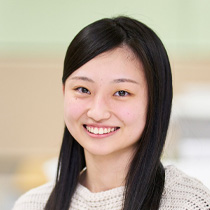
鏡味さん
アカウントSEとして働くことを目指しています。具体的には、企業と対話しながら、その企業が求めるシステムの開発をサポートし、プロジェクト全体のマネジメントを行う仕事になります。企業がシステムを導入する際、本当に必要な要件を言葉で明確に伝えられるとは限らず、潜在的なニーズを引き出す力が求められます。 そこで、研究で培った「知識の構造化」や「本質を見抜く力」を生かして、お客様が実現したいことを形にする仕事がしたいと思うようになりました。

オウさん
私の目標は、国際的なホテルのマネージャーとして活躍することです。そのために、まずは日本の一流ホテルで経験を積み、おもてなしの文化や高品質なサービスを学びたいと考えています。将来的には、ホテルの運営や管理にも携わり、より良いサービスを提供できる環境を整えることを目指しています。そういった意味でも、現在取り組んでいる「日本のホテル業界における外国人従業員のサービス向上」に関する研究は、貴重な経験になると思っています。

国見さん
医療分野でITを活用する仕事に就くことが決まりました。そこでは総合職として、医師向けの情報プラットフォームの運営や、製薬会社と医師をつなぐマーケティング支援などを行っていく予定です。僕自身、グローバルな環境で働きたいという思いが強く、海外での事業展開に関われる点も魅力に感じました。また、「人の体の動き」に関する研究テーマともリンクしている部分があるので、これまで学んできたことを活かしながら、医療業界に貢献していきたいと思っています。

西村教授
私の研究室では、学生自身が主体的に進路を決めるプロセスを大切にしています。就職活動については、JAISTの就職支援室がしっかりサポートしてくれるので、研究室として特別な指導は行なっていません。ただ、博士前期課程1年目の前期は授業や就活が大変なので、研究の負担を増やしすぎないように調整しています。研究は就活のためにやるものではありませんが、論理的に考える力や、データを分析し、分かりやすく伝える力は、どんな仕事でも必ず役に立つと思いますよ。
それでは最後に。ここだけの話、西村教授に伝えたいことはありますか?

国見さん
先生、そろそろダンスサークル復活しませんか?就活で忙しくて参加できなかったけど、また一緒に踊りたいです!

西村教授
国見君はすごいセンスがあるんだよね。4月の新歓でダンスを復活できたらいいなと思っているので、ぜひ一緒に踊りましょう。

龍さん
研究室のレイアウト、外の景色を見えるようにしたら、気分転換ができて研究がはかどるかも!

西村教授
ちょっと考えてみよう!でも、比喩的な意味での“外の景色”も大事だから、研究の視野も広げてみてね。
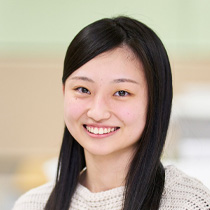
鏡味さん
もし修士論文が学術雑誌に掲載されたら、先生のダンスをライブで拝見したいです!

西村教授
論文化の道のりは決して簡単じゃないけど、ぜひチャレンジしてほしいですね。私もしっかりサポートしますよ!
