
研究開発イノベーション・社会課題解決のために何ができるのか、エビデンスをもとに考えます
政策のための科学研究室 Laboratory on Science for Policy
教授:小泉 周(KOIZUMI Amane)
E-mail: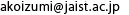
[研究分野]
政策のための科学、科学コミュニケーション、科学計量学、研究開発イノベーション
[キーワード]
大学の研究力、研究評価、政策立案、社会課題、科学コミュニケーション、研究開発マネジメント
研究を始めるのに必要な知識・能力
将来を見据えたビジョンをもつこと、それ以外、必要な知識や能力は、あとからでもついてきます。
この研究で身につく能力
将来を見据えた自分自身のオリジナルなビジョンのもと、自分が何を知りたいのか、何を解決したいのかを、様々な観点から掘り下げ、それを実現するためにロジックモデルを作り、どのようなエビデンスをどこから収集し、どのような分析を行えばよいのか、一緒に考えられたらと思います。その際、分野の枠をこえて、さまざまな観点でものをとらえ、考え、作り上げていくという思考方法が大切です(「越境する力(融合力)」)。さらに、さまざまなセクターをこえた協働をすすめることが大切であり(「巻き込む力(共創力)」)、そのためにも科学コミュニケーションを学ぶことがとても重要です(「コミュニケーション力」)。
こうした能力は、中央官庁や地方自治体、シンクタンク、大学経営・組織マネジメントなど、政策や企画立案、研究開発マネメントにおいて必要な能力です。また、こうした能力は、広く、医学・医療分野にも応用できると考えています。
【就職先企業・職種】中央官庁、地方自治体、シンクタンク、大学、医療関係など
研究内容
私自身の研究教育活動は、その原点となる医学者としての専門である医学生理学の専門性の追求とともに、それを軸とした社会との関わり、政策のための科学を遂行するところにまとめられます。
医学生理学の専門性の追求については、網膜神経節細胞の機能解明(網膜における視覚情報処理機構の解明)と、網膜における「超並列視覚情報処理」の在り方に取り組んできました。
さらに、そうした専門性を軸とし、専門的な「知識」を他分野にいかに伝え共創するか(「科学コミュニケーション」)を検証し、多様な視点から専門的「知識」を新たな価値創出に結びつける取り組みを行っています。
それらを踏まえて、政策・行政・社会の課題に対して科学がいかに貢献できるかを考える「政策のための科学」を実施します。たとえば、特に、大学の研究力評価などにおいて新たな定量的指標を提案(「厚み」)するなどし、文科省はじめ行政やメディアとともに、大学の研究力分析等に取り組んでいます。
上記を踏まえ、本研究室においては、以下の3点を重視した研究活動を行います。
① 知識の融合と新たな学問の芽の創出:
JAISTの優れた特徴である知識科学分野の研究との協働を中核にすえながら、様々な分野の「知識」を融合することにより、新たな学問の芽の創出を行います。そして、それを基盤として、新たな学問領域である「人類知性科学」の創出につなげます。
② 国・地域社会・産官学の連携により、既存の枠をこえた新たな価値創出:
アカデミアの枠をこえ、産学はもとより、国・地域社会との産学官連携(「政策のための科学」の実践)により、新たな価値創出(イノベーション)を促進します。
③ トランスファラブルなスキルをもった人材育成:
上記の実現を通じて、トランスファラブルなスキルをもった人材育成(特に、社会人教育や社会人リカレント教育、行政に関わる博士人材育成)をすすめます。
そして、上記3点を実現するために、「知識科学」が中心となりながら、「情報科学」や「マテリアルサイエンス」など他の分野との連携をはかり、それぞれの学問領域の「知識」(Intelligence)を融合し、さらに、人類の「知性」(Wisdom)へと昇華させることが重要と考えています。
このように「知識」を融合し「知性」として昇華させ発展させることで、人々の心や精神性、価値観までも対象に含めた新たな学問として「人類知性科学」の創出を目指します。
主な研究業績
- Neurite arborization and mosaic spacing in the mouse retina require DSCAM, Peter G. Fuerst, Amane Koizumi, Richard H. Masland, Robert W. Burgess, NATURE 451(7177) 470-U8 2008
- Reward research outreach in Japan, Amane Koizumi, Yuko Morita, Shishin Kawamoto, NATURE 500(7460) 29-29 2013
- Substantiality: A Construct Indicating Research Excellence to Measure University Research Performance. Masashi Shirabe, Amane Koizumi. Journal of Data and Information Science, July 25, 76-89, 2021
研究室の指導方針
一番大切なのは、自分が何を知りたいのか、何を解決したいのか、将来を見据えたビジョンを持っていることです。そして、そのためにできることについてロジックモデルをたて、色々なステイクホルダーを巻き込んで実現していく、実行力が重要でしょう。そのために出来ることを一緒に考えたいと思います。